甲府西高校の学園祭が今日から始りました。
今日は、県民文化ホールでダンス部や演劇部、3年次対抗等ありました。
もちろん ダンス部もまた中庭でやってますし、バザーやその他いろいろ楽しめる事が盛りだくさんです。
皆さん 見に来てね!
TEL.055-233-8873
〒400-0032 山梨県甲府市中央5-2-6
 太陽光を屋根の上に設置すると、施工が悪いと雨漏りの原因になります。結構、異業種参入で太陽光設置をする事が増え、クレーム発生がとても多いと聞きます。
太陽光を屋根の上に設置すると、施工が悪いと雨漏りの原因になります。結構、異業種参入で太陽光設置をする事が増え、クレーム発生がとても多いと聞きます。
当社でも施工研修等受け、屋根材に穴を開けてこんな補修でいいのか?と疑問に思う施工方法があります。
でも 建物に直接関係しない、ベランダやカーポートならいいのではないかと思います。
デザイン性はいまいちですが・・・・・
結構
見る人多数おりました。
みんな、リスクの少ない商品を
求めているようです。
多少の雨漏りはあるのかな~?
詳しい事はわかりません。
カタログも有りませんでした。
窓にガラスの飾り棚
小物を飾り
窓も開き
通風も得られます。
今回はこれが目玉?
棚板1セットで¥8,000円
ここは2セット使用されています。
棚受けが
新商品です。
棚板別途です。
2種類ありました。
これは
若い女子社員が考えたようです。
良いと思いますが、結構金額が高かった。
これの特徴
わかります。
長~い
玄関取っ手です。
小さなお子さんから
大きな大人まで
どんな人でも大丈夫
ユニバーサルな取っ手です。
玄関ドアです。
同じようなデザインの
勝手口ドアもありました。
これにも
ユニバーサルな
玄関取っ手を取り付けても
良いのでは?木目の
リースをかける
玄関ドアです。
今回は
どんなドアにも
付けられる
リース掛け
3種類ありました。
左 外部がすっきり見える
右側 従来品
色の見え方が違うのですが
写真だとわかりにくい!
そこに
ドアがついています。
すっきり仕上がって
見えます。
一体感があって
いいですよね。
掃き出しサッシ
デッキも我が家の
一部
お年寄りや子供も安全!
暑い日差しをよける
カーテンが
取り付きました。
直射日光が
上から入らなければ
暑い午後
ここでお茶でも出来そう。
もっと いろいろありましたが、今回人が多く、写真が撮りにくかった為、全部紹介できませんでした。
ショールームを持たない会社ですので、こういう機会で無いと現物を見れません。
次回 9月にアイメッセで展示されますので、是非見に来てください。
山梨県IC協会では、OZONでも照明講座を担当されている、河原武義先生をお迎えして最新の照明を学ぶセミナーを開催いたします。
今回は2回にわたって行われます。
第1回 『省エネの新しい照明手法』
日 時:6月22日(水) 14:00~16:00
受 付:13:30~
セミナー:住宅・オフィスの照明動向
間接照明技術
LED・EL時代の照明計画
光デザインの実演
1.カーテンライティングの技法
2.観葉植物ライティングの技法
3.アッパーコーニスの技法
第2回 『光のイメージ図プレゼンテクニック実習』
日 時:7月14日(水) 14:00~16:00
受 付:13:30~
セミナー:色鉛筆の使い方解説
平面と屋外パースの着色実習
発表・講評
場 所:県立青少年センター リバース和戸館2階
甲府市川田町517 TEL055-237-5311
費 用:山梨県IC協会会員 無料
非会員 2.000/1回 4.000/2回
希望者は
ヴィラ・デル・ソルでのランチコースは、予想外においしかった。
目でも楽しめます。
ホワイトアスパラおいしかった!
男子には、ちょっと少な目かな!
中はもっちり
このパン
初めて味わう食感でした。
おいしかった!
おいしかった。
結構 何回も入れて頂きました。
おいしいフランスパンに目がない
JKくやしがるだろうな・・・・・・
ハマグリはそのまま焼いてあり
味付けは海!
サザエは、エスカルゴのような味付けで
おいしかった。
そら豆も入っていたような
これも
さぱり
頂きました。
ランチは
つい 写真を撮り忘れます。
左側を少々食べてしましました。
鯛のうろこはパリパリ
身はしっとり。
おいし~い!
これも ナッツ類がメレンゲの中に
たっぷり
入っていました。
最後にコーヒーが出ましたが、写真撮り忘れました。
素敵な、コーヒーカップでした。
おいしいお料理に11人で、白ワインを4本あけてしまいました。
とても素敵な雰囲気の中で、ゆったり食事をすることができました。
 熱海駅からさほど遠くない相模湾を眼下に望む高台に、旧日向別邸は建っています。
熱海駅からさほど遠くない相模湾を眼下に望む高台に、旧日向別邸は建っています。
屋上を庭園とする地下室を利用してつくられた離れは、日本の文化と風土を愛したドイツ人建築家ブルーノ・タウトの設計によるものです。
熱海ってホント坂だらけの所です。平地は無いに等しい感じでした。
タクシーでここに来るまでも、自分で運転する気にはなれない細い道でした。
旧日向別邸はこの坂を、ず~と下った所にありました。
これが旧日向別邸の外観写真です。
タウトが設計した地下部分は、恐ろしく急な崖部分ですので写真には取れませんでした。
木々の間から、海沿いの下を走っている国道が見えます。
ここが玄関です。
残念ながら内部の写真撮影は禁止になっておりました。
実際にご自身の目でご覧になってください。
要予約になっているようです。
タウトが室内設計した部屋は、木造二階建て上屋擁壁を兼ねて造成された人工庭園(南海側)の地下部分にありました。
地下室へは、上屋1階居間の既設木戸からと、玄関左木戸との2ヶ所ありました。
地下室に下りてゆくと、ニッチ・社交室(ピンポン室)・洋間・和室・ベランダが微妙な角度を持って空間構成されていました。
それぞれの部屋は、社交室(ベートーベン)・洋間(モーツアルト)・和室(バッハ)と名づけられているようです。
タウトは、ナチス・ドイツに追われ、日本を訪れ高崎の禅寺少林山達磨寺で暮らしながら、桂離宮、伊勢神宮などの日本の伝統美の再発見に貢献し数々の著書を残しているそうです。
この建物は、篤志家が平成16年に取得され、同年11月に熱海市に寄付されたそうです。
平成18年7月に国の重要文化財の指定を受けたそうです。
起雲閣は、庭を囲んでぐる~っと一周できるようになっています。
1990年に新築された建物です。
初霜
春風
有明の3部屋が見学できます。
文豪たちの顔写真が所狭しと並んでおります。
桜井兵五郎が旅館を営んでいた頃の部屋です。
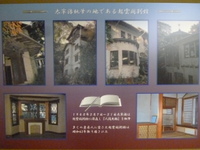 この写真は、太宰治がここで『人間失格』を執筆されたそうです。昭和63年に取り壊されてしまった、起雲閣別邸とのことです。
この写真は、太宰治がここで『人間失格』を執筆されたそうです。昭和63年に取り壊されてしまった、起雲閣別邸とのことです。
どんな建物だったのか現物を見たかったのですが、無くなってしまっておりとても残念です。
多くの著名人に愛されたそうです。
春風の間です。
ここにも
昭和の大作家達の品が展示されておりました。
熱海って文豪たちに愛されていたんですね。
この部屋が、一番落着いた感じでした。
春風の間は、泊まっても落着かないなと思う壁の色でした。
色によって、気持ちが違ってくるのを体感できる3部屋でした。
桜井氏が旅館をされていた頃の浴場です。
熱海の浴室って、山梨にある温泉施設より浴室が小さいように感じたのですが気のせいでしょうか?
カランの数もすくなかったです。
旅館は1999年に廃業されたとの事です。
当初は、麒麟に隣接して立てられていたようですが、2度にわたり移築され、現在の場所にあるようです。
良いたたずまいです。
90年以上経っていても、風情があります。
でも 廊下側の長押は一本物を使っていたりとお金かけた建物のようです。
何故 昔の建物は移築しやすいのかというと、現在の建物のように釘と金物でガチガチに止めてないからです。
現在の建物は、一度壊れたら、ゴミになるしか有りません。
ある先生が、木は一本一本性格が違うんだから、それを一律にして構造計算する事事態が間違っているとおっしゃっておられました。
これが 有名な『根津の大石』のようです。
推定約20トン
20人の庭師が2ヶ月近くをかけて運んだといわれているそうです。
鶴が気になって撮りました。
熱海にある起雲閣は、大正から昭和にかけて3人の富豪と共に歴史を歩んできたそうです。
鎌倉末期~室町初期の武家又は公家の屋敷などに現れた門形式の1つとのことです。 医師の家の門としても使われ、病人の往来を妨げないように門扉は設けないものとされてましたが、実用面から扉を設けるようになったとのことです。
内田信也は、大正・昭和期の政治家、実業家。三井物産を経て内田汽船を設立し、第一次世界大戦景気で財をなし、海運王と呼ばれたとのことです。
主に実母の静養の場所として、別荘を利用されたとのことです。
麒麟(1階)と大鳳(2階)の各部屋、玄関が現存していました。
壁の青が印象深い部屋です。
麒麟は、三方たたみ廊下を配し、床の間や付け書院を構えた10畳と8畳の和室です。
障子の桟が凝ったつくりになっていました。
1階と逆の8畳10畳の部屋の取り方です。
壁は紫
ここも1階に負けないインパクトの強い部屋でした。
壁の色で、こんなに受ける印象が違うのだという事を改めて思い知りました。
竹材を用いた障子は、初めて見ました。
外観和風、中洋館です。
根津氏も明治・昭和期の政治家、実業家でした。
1905年に東武鉄道社長になり、1929年日光線を開通させ鉄道王と呼ばれたそうです。
正面中央に暖炉を据えた様式のデザインを基本にしていますが、
桃山風な天井や、長押を廻した真壁、欄間、建具などに和風の造作見られ、日本的建築の特徴や中国的装飾、アールデコが彩るなどいろんな文化が入っているようです。
お金かけてるな~
昔のお金持ちってすごいと思いました。
ところで山梨にも、根津嘉一郎の生家があります。
このj部屋は、中世英国のチューダー様式とのことです。
英国の建築様式や“名栗仕上げ”(手斧で削った材料や仕上げの方法)を取り入れたヨーロッパの山荘風の仕上がりに見せています。
荒削りな木の装飾にびっくり!
ステンドグラスの天井とタイルの床が印象的でした。
アール・デコのデザインを基調としているとのことです。
ガラスは当時のままなので、波打って見える外部のい景色がまた良い味わいになっています。
1929年、根津嘉一郎により建てられた洋館です。
格調高い迎賓の雰囲気があふれており、かつての栄華を今に伝えているようです。
時間が無く、ゆっくり見学が出来ませんでしたが、また是非ゆっくり見学したい部屋です。
床・壁の内装から浴槽の使用まで当時の姿を再現したものだそうです。
窓のステンドグラスや装飾的な湯出口は創建当時のものを用いているそうです。
昔の浴槽って今のものに比べて深い気がするのですが、立ってお湯につかっていたのでしょうか?
浴槽二つも
熱いお湯とぬるいお湯を入れていたのでしょうか?
熱海にある『スコット』旧館は、滋賀直哉も通った有名なレストランのようです。
よくグルメ雑誌に出てきます。
店内は
こじんまりとした
少人数向けです。
今回は、10人で行きましたので
こちらで
お料理を頂きました。
全員が集まるのを待っている
間にも
たくさんのお客様が、タクシーでお店に
食事しにいらしていました。
全体的な感じは
他のお客様が
映るのは困りますと言う事で
私たちの食べるテーブル席の
写真を撮りました。
ワクワク!
これは、オニオングラタンです。
ぐつぐつ煮立ったスープは
とても
熱かった。!
猫舌の人は、困っていました。
トマトクリームスープです。
もう一種類
コーンクリームスープがあったようですが
写真撮れませんでした。
この かにクリームコロッケか
ハンバーグのどちらかを選ぶと言う事でした。
これは 隣の人が注文したものです。
このハンバークを注文しました。
ソースが香ばしく
ハンバーグも
肉を食べているって感じでした。
2コ付いてきました。
バターが
ころころしており、かわいらしかった。
でも2コは食べれませんでした。
コーヒーを頂きました。
このコーヒー
街案内のパンフレットを見せると
サービスでいただけます。
ちょっと 耳寄り情報です。
山梨県インテリアコーディネーター協会の第2回スキルアップセミナーに行ってきました。
今回は、県内に工場がある日本の金物メーカーである『ムラコシ精工』さまです。
お忙しい中、多くの社員の方に接待して頂きました。
 ムラコシ精工さま3階にある研修室をお借りして研修いたしました。スマップの信吾君が出たムラコシ精工の耐震ラッチについてのTV放送を見せていただきました。
ムラコシ精工さま3階にある研修室をお借りして研修いたしました。スマップの信吾君が出たムラコシ精工の耐震ラッチについてのTV放送を見せていただきました。
阪神淡路大震災の時には、食器棚等の耐震ラッチが話題になり、各キッチンメーカーが耐震ラッチ付きの吊戸棚など出しておりましたが、いま付いています?
自社で、金型を作られたり、生産ラインを構築されたりして、海外の安い金物に負けないよう研究されてきたそうです。
山梨に、このような素晴らしい会社があったとは知りませんでした。
メーカーから持ち込まれたムラコシ精工の金物を使った商品の耐久実験をするところです。
扉を開閉する装置があり
いくつも実験されておりました。
全てコンピューター制御でロボットが全て仕事をしており、人間はずいぶん少ない人数でした。
金型で形を作り、それが全て金型から取り出せたかセンサーでチェックして製品になります。
別の商品を作っている工場です。
協力工場で出来た部品を組み合わせて製品を作り上げます。
もちろん 自動制御のロボットがやります。
これも 出荷先をしっかり確認できるシステムを構築されたそうです。
ISO1001やISO1014を取得され
各自自信をもって仕事が出来る環境を作られたとのことです。
社員の為のショールームがあります。
働いている方が、自分たちの作っている物が、どんな物になるのか理解してもらう為につくられたそうです。
ちゃんとしたショールームは新宿OZONにあり、工場の様子がモニターで見ることが出来るそうです。
今日の勉強会も映っていたのでしょうか?
とても 素晴らしい工場を見学させていただきました。
ムラコシ精工の皆様、ありがとうございました。
偶然 天野太郎氏の建築展を見る機会がありました。
場所は東京藝術大学大学美術館陳列館です。
明日23日までやっております。
天野氏は、1918年広島県呉市で生まれています。
1942年、早稲田大学理工学部建築学科入学。
在学中に会津八一氏(日本の歌人・美術史家・書家)に師事されたとの事です。
ライトの弟子であった遠藤新氏の薫陶を受け、1952年にフランク・ロイド・ライト氏のいるタリアセンで直接師事した数少ない日本人との事です。
1955年工学院大学建築学科助教授となられ、教育の傍ら設計活動を始められたとの事です。
吉田五十八氏が退官された東京藝術大学に招かれ、教鞭をとられながらキャンバス計画を指揮されたそうです。
日本の伝統的空間を評価され、生活や社会に即した建築が建てられる環境とはどうあるべきかを考察し、戦後のモダニズムを昇華させようと努められたそうです。
会場には、多くの先生に関わりのある建築家の方々がいらっしゃいました。
山梨でも増穂体育館が、天野吉原設計事務所の手によりものだそうです。